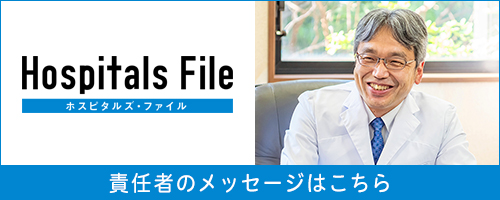院長挨拶

東京病院の前身は、昭和6年設立の清瀬病院と昭和14年設立の東京療養所が昭和37年に合併して現在の地に完成した、国立療養所東京病院です。
平成16年4月に、独立行政法人国立病院機構東京病院となり、当初の結核専門の病院から、建物も診療内容も大きく変わってきました。
手元に東京病院の50周年記念誌があります。
国立療養所東京病院開設から50周年に当たる2012年を目途に作成されたものですが、そこには、東京病院が日本で初めて行ったこととして、
抗結核薬化学療法治験、リハビリテーション医学の導入、リハビリテーション学院設立、C型肝炎ウイルス発見への寄与、 エイズ緩和ケア病棟開設、ブロンプトンカクテル導入などが紹介されています。
さらにそのころを境に、地域医療を担う急性期病院として発展し、地域災害拠点病院、二次救急医療機関、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関などの指定を受けてきました。
また、診療の幅を広げる中で、東京都アレルギー疾患医療専門病院、東京都がん診療連携協力病院(肺がん)などの指定も追加されました。
医師の研修医療機関としての機能の充実も図り、内科専門研修の基幹病院、また連携病院としてのみならず、その先のサブスぺシャリティー分野の研修においても、
基幹病院、連携病院として、研修の受け入れを行っています。
東京病院は、「患者さん」の満足度を高め、「地域」に必要とされる病院になることはもちろん、同時に「職員」の教育体制の充実に努力していることも、強調しておきたいと思います。
医療や看護の質、医療安全、教育・研修、広報などの方面に関しては、病院機能評価によって外部評価を受けています。
2011年に日本医療機能評価機構の認定を初めて受け、5年ごとに更新しています。
今年度も、東京病院が目指す方向性の4つの柱には大きな変更はありません。
(1)日本の呼吸器センターであること
呼吸器疾患の患者さんの入院数を、公開されているデータに基づいて、日本全国の病院と比較することができます。患者数という目に見える数字での一番を目指すのはもちろんですが、首都圏のお医者さんからも、患者さんやそのご家族からも「東京病院に行っていれば間違いないね」「肺の病気で困ったら、東京病院に行けばいいね」という感覚で信頼してもらえるようにすることが理想形です。また、将来の呼吸器専門医を目指す医師の研修病院としての人気も維持し続けていきたいと思います。
(2)地域の病院として頼りになること
どうすれば、この地域に住んでいる人やこの地域で診療してる人から信頼されるのかと考えれば、総合病院を作って救急医療もやってすべての診療科に優秀な先生を連れてきて、最新の医療機器を購入したらいいんですが、それは非現実的です。当院が理想の病院である必要はなくて、この地域の医療施設すべてが有機的につながっていて、この地域の人が医療に関しては困っていないことが重要です。そういう地域の中で、当院だけで理想の病院を作るのではなく、役割を分担しながら、この地域の人がこの地域に住んでいてよかったと思える地域であること、その中で、東京病院は頼りになるといわれることが理想の形です。
(3)他の病院にあまりない機能をもち補完すること
当院は一般病院でありながら、複合機能として、緩和ケア病棟、結核病棟、神経難病中心の障害者病棟、回復期リハビリ病棟を運営しています。肺がんを中心にがんの診断、治療の専門病院でありながら、緩和ケア病棟も持つことは大事にしていきたいと思います。がんと分かったら、がん専門病院で見てもらったほうが安心と考えるかもしれません。でも、がん専門病院で診るのは、合併症が少ない、治療のできるがん中心ですから、がん難民がでたりします。家から近い地域の病院の良さは守って、治すことのできない病気であっても、この地域で療養することの役割も担っていたいと思いますし、国立病院としてのセーフティーネット系医療の役割も果たしたいと思います。
(4)慌ただしい感じがなく、優しくいい雰囲気を持っていること
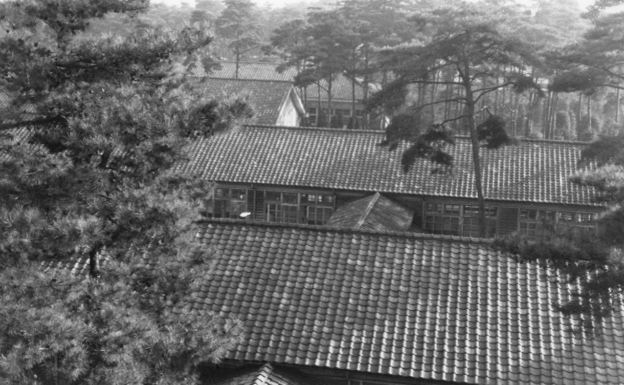
病院機能の理想について挙げてきましたが、病院の雰囲気も大事にしたいと思っています。 病院という機能上、患者さんも職員もなかなか楽しく過ごしてばかりはいられません。 つらいことがあって、うまくいかないこともある中で、お互いが相手を思いやる。 医療職が患者さんにやさしいのはもちろんですが、患者さんが職員にやさしいのもこの病院の特徴であり、 私の理想形です。外来の時には多くの患者さんから励ましの言葉をいただきます。

よい病院は東京病院の職員だけではできません。 当院を受診される患者さんのみではなく、この地域の方々もより良い東京病院づくりに ぜひ参加をお願いします。
2025年4月1日
国立病院機構東京病院
院長 松井 弘稔